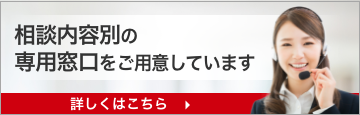労働審判で会社側が不利にならないための基礎知識
- 労働問題
- 労働審判
- 会社側
- 不利

令和3年(2021年)には、全国の裁判所で3609件の労働審判の申し立てがなされました。
労働問題を解決する手続きのひとつが労働審判ですが、労働審判は、会社側にとって不利な印象を持っている方もいるのではないでしょうか。
本コラムでは、労働審判の手続きや、会社側が不利と思われる原因などについてベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。
1、そもそも労働審判とは
まずは労働審判がどのような手続きなのか解説します。
-
(1)紛争解決手続の種類
会社と従業員の労働問題に関する紛争の解決手段といえば、裁判(通常の民事訴訟)をイメージされる方が多いのではないでしょうか。しかし、労働問題を解決する手続きは労働審判をはじめとして、裁判以外にもあります。
以下では、裁判所やそれ以外の行政機関による、労働紛争を解決するための手続きの種類を紹介します。・裁判(民事通常訴訟)
民事の通常訴訟は、事件について裁判所が終局的な判断を下すことを目的にする手続きです。通常の民事訴訟は、原告が訴状を裁判所に提出して、訴えを提起することによって開始されます。その後、弁論準備手続などによって争点や証拠の整理を経て、証拠の調べがなされたのちに、判決が下されることになります。
また、東京や大阪に横浜などの大規模な地方裁判所には、労働事件を専門に扱う部署も置かれています。
・労働審判
労働審判については次項で詳しく解説します。
訴訟手続とはさまざまな点が異なり、特色のある手続きです。
・民事保全手続
民事保全手続は、前述した通常訴訟による権利の実現をあらかじめ確保するために、簡易迅速な審理によって、裁判所が仮の措置(仮処分・仮差押え)を命じる暫定的な手続きです。
労働事件では、解雇された者が従業員である地位の保全や賃金の仮払いを内容とする処分を求めるかたちでこの保全手続が利用されることが多くあります。
・少額訴訟手続
訴額が60万円以下の金銭を請求する事件については、簡易裁判所によって審理される少額訴訟の手続きを利用することができます。
少額訴訟手続では、原則1回の期日で審理が完了します。
・民事調停
労働審判手続の中で話し合いによる解決が試みられますが、労働審判とは別の手続きとして民事調停法に基づく民事調停も利用することも可能です。 -
(2)労働審判とは
労働審判制度は、解雇や給料の不払いなど、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを対象として、紛争の実情に即した適正かつ実効的な解決を図ることを目的とした手続きです。
労働審判法は労働審判制度を具体化するものとして、2004年(平成16年)5月に国会で成立し、2006年4月から施行されて労働審判制度がスタートました。
労働審判には、以下のような特徴があります。- ① 原則として期日が3回以内
- ② 裁判官である労働審判官のほか、労働関係の専門的な知識を持つ労働審判員からなる労働審判委員会が事件を審理
- ③ 調停の成立による解決を試み、調停による解決ができない場合には、審判を行う(調停の優先)
また、労働審判の手続きは、下記のような流れで進みます。
- ① 労働審判手続は当事者の申し立てにより開始されて、裁判所で内容の形式的なチェックが行われたのちに、会社へ申立書の写しなどが送付されます。
- ② 期日は、原則として3回以内です。
申し立てから40日以内に第1回期日が指定されます。会社としては、第1回期日の前の指定された日までに反論の書面を提出する必要があります。 - ③ 労働審判委員会は、申立書、答弁書などの主張や書証、審尋(しんじん)などの結果に基づき、心証を形成しつつ、当事者間で合意が可能かどうかを検討し、当事者に調停の打診を行います。
調停が成立する場合には、第1回期日や第2回期日での成立することが多いです。 - ④ 3回の期日によっても調停成立の見込みが立たない場合には、原則として、労働審判となります。
実務では期日における口頭告知による審判が主流であり、口頭告知を受けてから2週間以内に異議の申し立てをしないと労働審判は確定することになります。 - ⑤ 労働審判に異議がなされた場合には、労働審判申立時に提訴したものとみなされて、民事訴訟に移行するのが原則です。
-
(3)労働審判によって会社が受けるダメージ
会社が労働審判を申し立てられると、その労働審判に対応するために、弁護士に報酬を支払わなければならなくなる可能性が高いです。また、労働者の請求が認められると、申立人である労働者にも金銭を支払わなければならない可能性があります。
そして、申立人の主張に反論するための書面作成・証拠収集、会社関係者の期日への出席などの負担も発生します。
さらに、労務管理見直しの必要が発生したり、会社に対する信頼が低下したりするおそれもあり、同様の問題が他の従業員へ波及する可能性もあります。
2、労働審判は会社側に不利になりがち! その原因とは
労働審判は、下記のような原因から、会社側にとって不利と思われる側面があります。
-
(1)準備期間が短いため
労働審判が申し立てられた後、労働審判規則によれば40日以内に第1回期日が指定されることになっています。
申し立てがあったのち、会社に申立書などの資料が郵送されて初めて会社は申し立ての全容を知ることになります。従業員からの申立書が会社に郵送されて申し立ての内容を把握してから、答弁書(反論文書)の締め切りまでは通常1か月もありません。(20日強であることが多いといえます)。
そのため、労働審判の申し立て前から十分に準備する機会のあった申立人と比べて、会社側は反論を準備する時間が非常に短いといえます。
さらに、第1回の期日は、労働審判において大変重要な期日であり、第1回の期日までに会社はしっかりと主張を尽くさなければ、裁判所には申立人に有利な心証が形成されてしまうおそれがあります。
訴訟のように「具体的な認否や反論は追って次回以降の期日で行う」とする、いわゆる三行答弁書を出すわけにもいかないのです。 -
(2)労働法令の性質上、労働者への保護に手厚いため
労働関係法やその判例法理は労働者への保護に手厚いという性質があり、どうしても労働者側に有利に進展しやすくなる傾向があります。
たとえば、解雇権濫用法理や残業規制などは労働者の権利を守るために存在しているものです。
そのため、解雇や賃金や残業代請求などについて、会社側が日頃から法令を意識した十分な対応をしてこなかった場合には、厳しい結果となる可能性は高いでしょう。
3、労働審判が決裂したとき・24条終了したときは訴訟に移行
労働審判で解決しなかった場合には、訴訟に進むことになります。
-
(1)訴訟への移行
訴訟の流れは以下のとおりです。
・労働審判
労働審判委員会は、調停による解決ができない場合には労働審判を行います。
労働審判は、その主文および理由の要旨を記載した審判書を作成して行うのが原則ですが、前述のとおり期日における口頭告知も認められており、実務では口頭告知が大半です。
口頭告知の内容は、調書に記載されることになります。
・労働審判への異議
労働審判の結果に対しては、審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申し立てを行うことができます。
期間内に異議の申し立てがないときには審判の結果が確定しますが、異議が出された場合には労働審判は失効して労働審判申立時に提訴したものとみなされて、通常訴訟に移行することになります。
・24条終了
労働審判法24条では、事案の性質から労働審判手続を行うことが適当でないと認められる場合には、労働審判委員会は労働審判事件を終了させることができる旨が定められています。
審判手続は、簡易迅速な手続きであることから、争点が多岐にわたる複雑な事件などは労働審判による解決にはなじみません。
そこで、事案の性質によって労働審判を終了させられるように定められており、これを「24条終了」といいます。
24条終了があった場合には、労働審判申立時に提訴したものとみなされて、通常訴訟に移行することになります。 -
(2)訴訟と労働審判の違い
以下では、訴訟と労働審判の違いについて解説します。
・期日の回数
労働審判の期日は原則として3回以内であり、期日の回数が制限されています。
しかし、訴訟では、このような期日の回数制限はありません。
したがって、訴訟では解決(判決または和解)までの期間が長くなることが多いといえます。
労働審判は多くの場合には申し立てから3か月程度で終了するのに対して、訴訟は1年を超えることも少なくありません。
・審理する者や期日の内容
労働審判の審理では、裁判官と裁判官ではない一般の労働事件の専門家も含む労働審判委員会によって審理され、期日における協議を含め柔軟な解決が志向されます。
一方、通常訴訟では、原則として裁判官のみによって審理されることになり、もちろん和解に向けた協議が行われることはありますが、労働審判のような柔軟な解決までは志向されません。
4、労働事件で弁護士ができること
労働事件では、労働審判が申し立てられた場合には、弁護士が会社の代理人になって対応することができます。
労働事件は専門的な知見が必要になるため、弁護士に相談することをおすすめします。
また、顧問弁護士と契約を結んでいれば、労働審判の申し立てがある前の段階から準備をすることができます。
労働審判は準備期間が非常に短いため、申し立てをされてから弁護士を探し始めるのでは準備期間はますます短くなってしまい、より一層不利になるおそれもあります。
労務管理の一環として、日頃から顧問弁護士に適切に相談を行い、トラブルなどがあれば適宜共有しておくことが大切です。
5、まとめ
労働審判の申し立てがなされると、会社としては非常に短い期間で対応することを余儀なくされます。
そのため、申し立てがあった場合には、すぐに弁護士に相談することが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、労働事件について豊富な実績があり、労働審判について対応することが可能です。
また、各企業のニーズに合わせた、柔軟な顧問弁護士サービスも提供しております。
労働問題への対応や顧問弁護士契約は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスにご依頼ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています