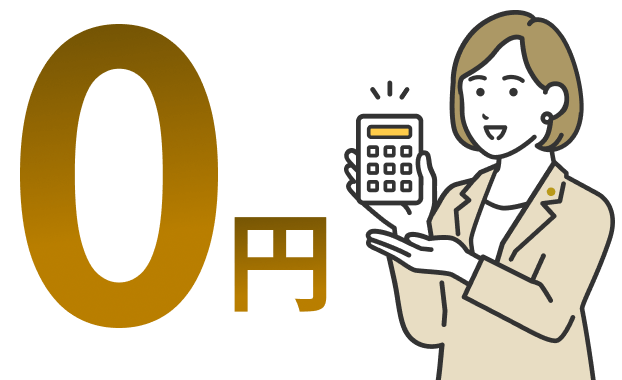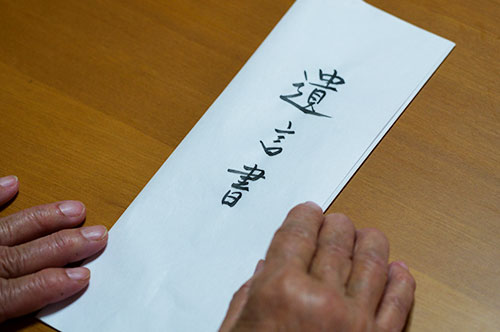一人暮らしの独身が死亡したときの遺産相続!法定相続人や相続放棄
- 遺産を受け取る方
- 一人暮らし
- 死亡
- 相続

一人暮らしの人が亡くなったときには、誰がその人の遺産を相続するのか、ということが問題になります。
一人暮らしでも家族がいればその人が遺産を相続することができますが、生涯独身で兄弟姉妹がおらず、特別縁故者もいない場合には、誰も遺産を相続できる人がいません。この場合には、最終的には遺産は国庫に帰属することになります。
本コラムでは、一人暮らしをしている独身の家族が死亡した場合の遺産相続について、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。


1、独身で一人暮らしの家族が死亡したときの法定相続人
被相続人が亡くなった場合に、遺産を相続することができる人を「法定相続人」といいます。法定相続人の範囲と順位については、民法で以下のように定められています。
- 配偶者……常に相続人になる
- 子どもや孫などの直系卑属……第1順位の相続人
- 父母や祖父母などの直系尊属……第2順位の相続人
- 兄弟姉妹……第3順位の相続人
相続が開始したときは、上記の法定相続人の範囲および順位をふまえて、相続人を確定していくことになります。
独身の家族が亡くなった場合には、配偶者および子どもはいないため、以下の人が遺産を相続することになります。
独身で一人暮らしの被相続人の父母が健在なら、父母が相続人になります。
父母のどちらか一方が亡くなっている場合には、残されたもう一方の親が相続人になります。
被相続人よりも先に父母が亡くなっており、祖父母が健在である場合には、祖父母が法定相続人となります。
もっとも、被相続人が高齢であった場合には祖父母が相続人になる可能性は低いでしょう。
② 兄弟姉妹
被相続人の父母や祖父母がすでに亡くなっているときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
独身で一人暮らしの相続人が高齢だった場合には、両親もすでに亡くなっているので兄弟姉妹が相続人になるケースが多いでしょう。
2、被相続人が独身だったときの遺産相続の注意点
被相続人が独身だった場合の遺産相続については、以下の点に注意が必要です。
-
(1)代襲相続により甥・姪が相続権を取得することがある
代襲相続とは、本来相続人になる人がすでに亡くなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続する制度です。
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていたとしても、兄弟姉妹に子ども(被相続人からみた甥・姪)がいる場合には、代襲相続により甥・姪が相続権を取得することになります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続が認められるのは、1代に限ります。
甥や姪が被相続人よりも先に亡くなっていたとしても、さらに下の世代に相続権が移ることはありません。 -
(2)異母(異父)兄弟がいる場合には相続分に差が生じる
被相続人の親が離婚して、再婚をしていた場合には、母または父を異にする兄弟姉妹が存在することがあります。
このような異母(異父)兄弟が相続人になるときは、相続人間で相続分に差が生じることがあります。
具体的には、片親のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
たとえば、被相続人が死亡し、被相続人には、両親を同じくする兄弟Aと父のみを同じくする兄弟Bがいたとします。
この場合の相続分は、以下のようになります。
- A……3分の2
- B……3分の1
-
(3)嫡出子と非嫡出子で法定相続分に区別はない
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指す言葉です。以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とされており、嫡出子と非嫡出子との間の法定相続分に差がありました。
しかし、平成25年の最高裁決定により、嫡出子と非嫡出子との間で相続分に差を設けることは違憲と判断された結果、現在では、嫡出子と非嫡出子との間で法定相続分に差はありません。
3、一人暮らしをしていた被相続人の遺産を誰も継がない場合
遺言書がなく、相続人が誰もいない、またはすべての相続人が相続放棄をした場合には、一人暮らしの被相続人の遺産を相続する人が誰もいなくなってしまいます。
以下では、このような場合の手続きについて解説します。
-
(1)相続財産管理人が遺産を清算する
一人暮らしをしていた被相続人が死亡し、相続人が誰もいないときは、利害関係人(債権者や特別縁故者)または検察官からの申立てによって、相続財産管理人(相続財産清算人ともいいます。)が選任されます。
相続財産管理人とは、相続人がいない相続財産を最終的に国庫へ帰属させる役割を担う人をいいます。しかし、相続財産を管理する人がいない状態では、国庫へ帰属させることはできません。そこで、裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産を国庫に帰属させるまでの必要な職務を行わせることになっているのです。
具体的には、相続財産管理人は、相続人の捜索を行うとともに、相続財産の管理・処分を行い、相続債権者や受遺者への弁済を行います。
つまり、相続人が誰もいないときの遺産は、まずは相続債権者や受遺者への支払いに充てられることになるのです。 -
(2)特別縁故者がいる場合にはその人に引き継がれる
特別縁故者とは、以下のいずれかに該当する人のことをいいます。
- 被相続人と生計を同じくしていた人
- 被相続人の療養看護に努めた人
- その他特別の縁故があった人
特別縁故者に該当する人は、裁判所に財産分与の申立てをすることより、相続財産の全部または一部を受け取ることができます。
また、相続財産管理人による相続債権者および受遺者への清算手続きを終えても相続財産に余りがある場合には、裁判所の決定により、相続財産の分与を受けられます。
なお、どの程度の財産を分与されるのかは、裁判所が判断することになります。
裁判所の判断によっては、相続人が誰もいなかったとしても特別縁故者が財産分与を受けられないこともあるという点に注意してください。 -
(3)誰も遺産を引き継ぐ人がいないときは最終的に国庫に帰属する
相続債権者および受遺者への弁済や特別縁故者への財産分与を終えても、まだ相続財産に余りがある場合には、相続財産管理人によって、最終的には国庫に帰属させられることになります。
お問い合わせください。
4、遺産相続の悩みを弁護士に相談するメリット
以下では、弁護士に遺産相続に関する悩みを相談するメリットを解説します。
-
(1)遺産相続の手続きをサポートしてもらえる
遺産相続の手続きは、単に遺産を分ければよいというわけではありません。
遺産分割協議をする前提として、まずは誰が相続人であるかを確定させなければならないため、相続人の調査が必要です。相続人に漏れがあると遺産分割協議をやり直さなければならないため、正確に調査することが大切です。
また、遺産相続の対象となる相続財産の調査も必要になります。とくに一人暮らしの家族が亡くなった場合には、亡くなった本人以外の人がどこにどのような財産があるかを把握していることはまれであるため、一から手探りで探していかなければならなくなります。
相続人調査や相続財産調査は、専門的な知識や経験がなければ、正確な調査を行うことも困難です。
弁護士であれば、専門知識と豊富な経験に基づき、迅速かつ正確な調査を実現することができます。 -
(2)代理人として交渉をしてもらえる
遺産相続のトラブルは、身内同士であるためお互いに遠慮がなくなり、争いが激化する傾向があります。
第三者である弁護士が遺産分割協議に介入すれば、他の相続人も冷静さを取り戻して、論理的な話し合いを実現しやすくなります。
また、話し合いで解決できない問題については遺産分割調停や審判により解決することになりますが、それらの法的手続きについても弁護士ならサポートしてくれます。 -
(3)正当な権利を主張し、有利に遺産相続を進めることができる
遺産相続では、特別受益の持ち戻しや寄与分といった相続分の修正要素が存在しています。
これらの制度を利用できる状況であるにもかかわらず、制度自体を知らずに遺産分割に応じてしまうと、本来の取り分よりも少なくなってしまう可能性があります。
遺産相続にはさまざまな制度があるので、状況に応じた適切な権利を主張していくためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
5、まとめ
一人暮らしの独身者が亡くなった場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることが多いです。
そのような場合には、異父(異母)兄弟間の相続分の違い、甥・姪に対する代襲相続など、注意すべきポイントが複数存在します。
一人で手続きを進めていくのが不安な方は、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスまでお気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています